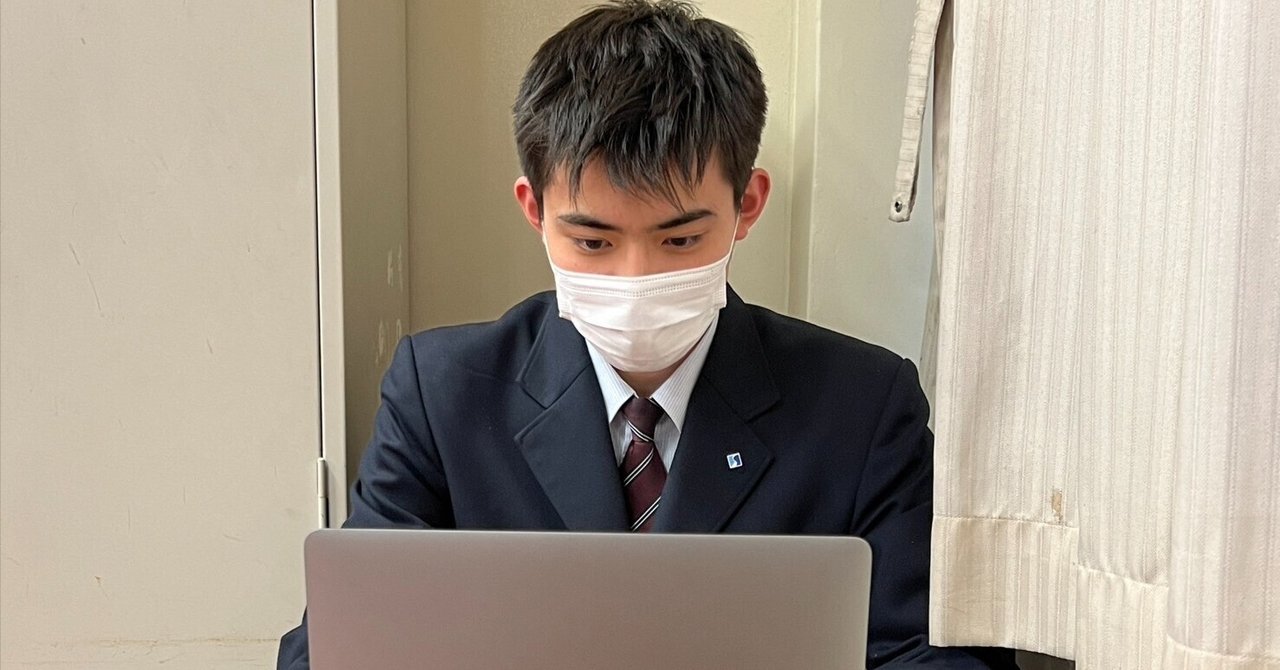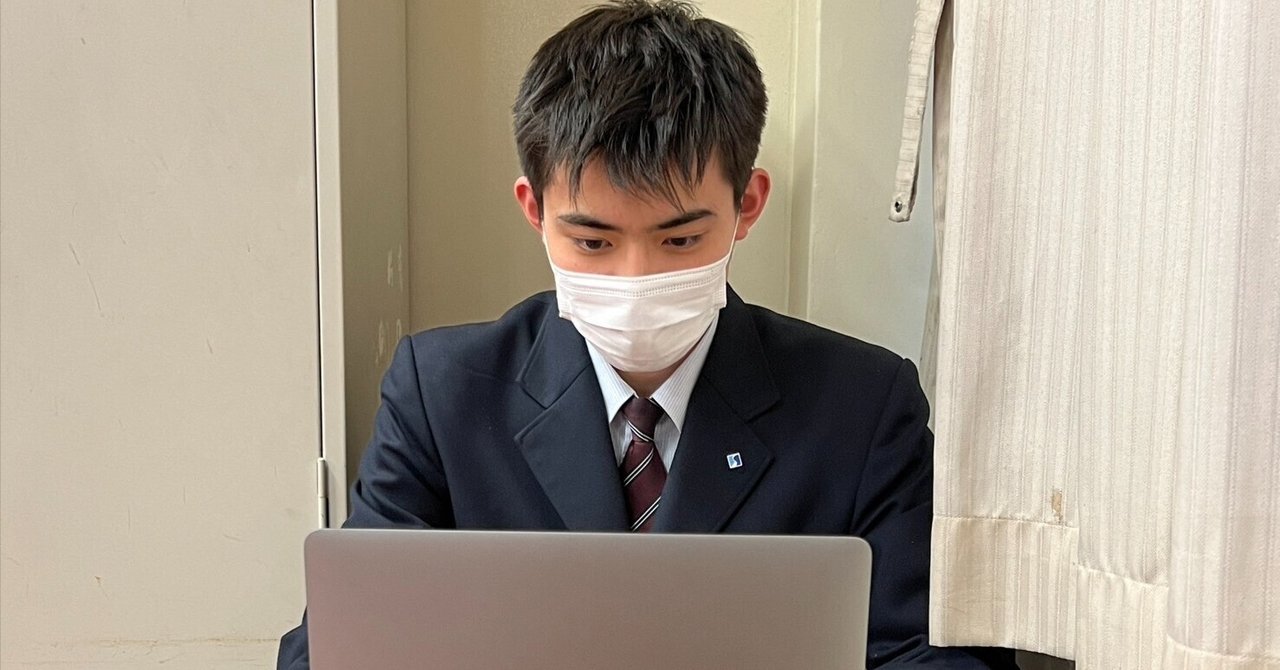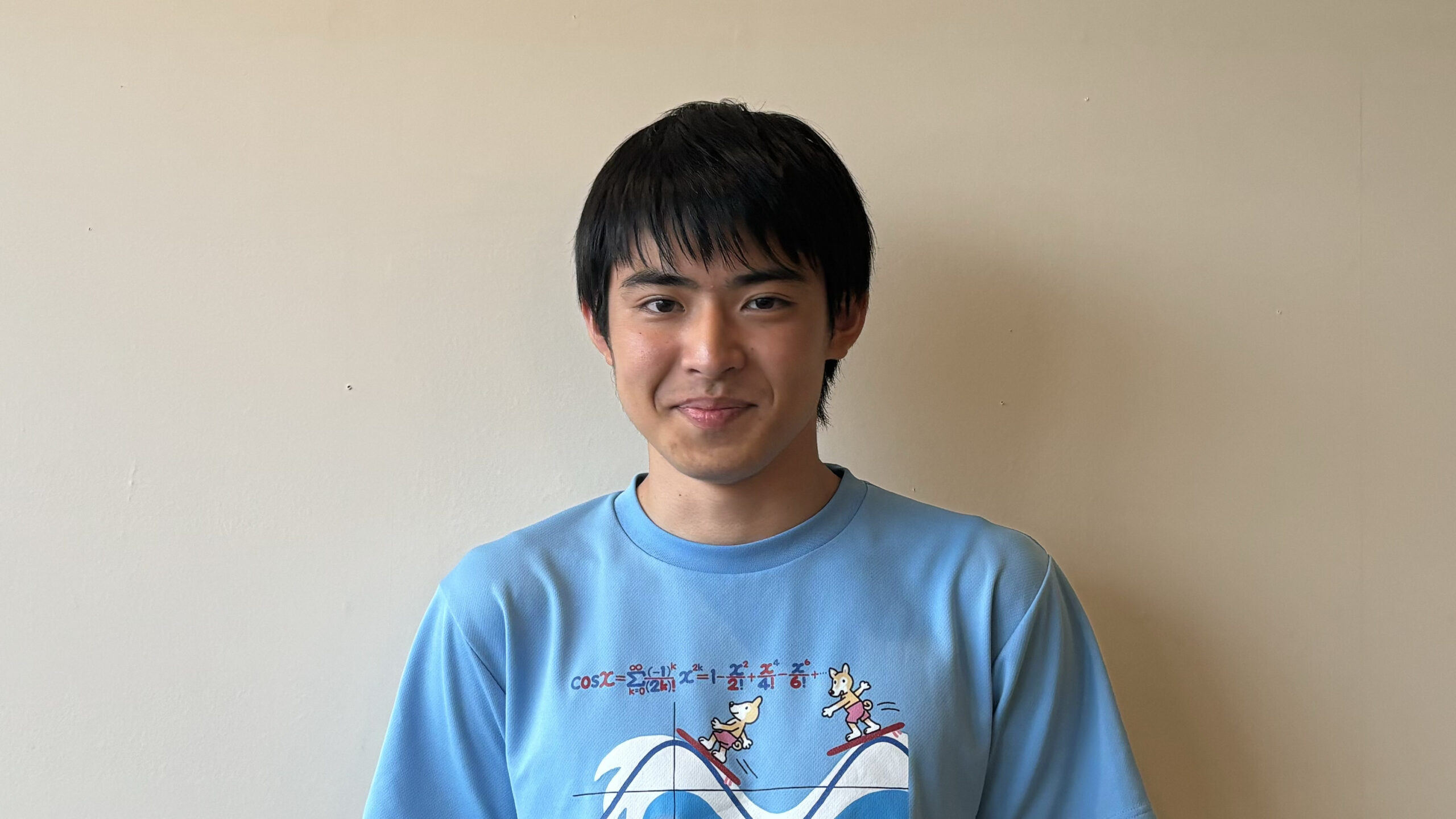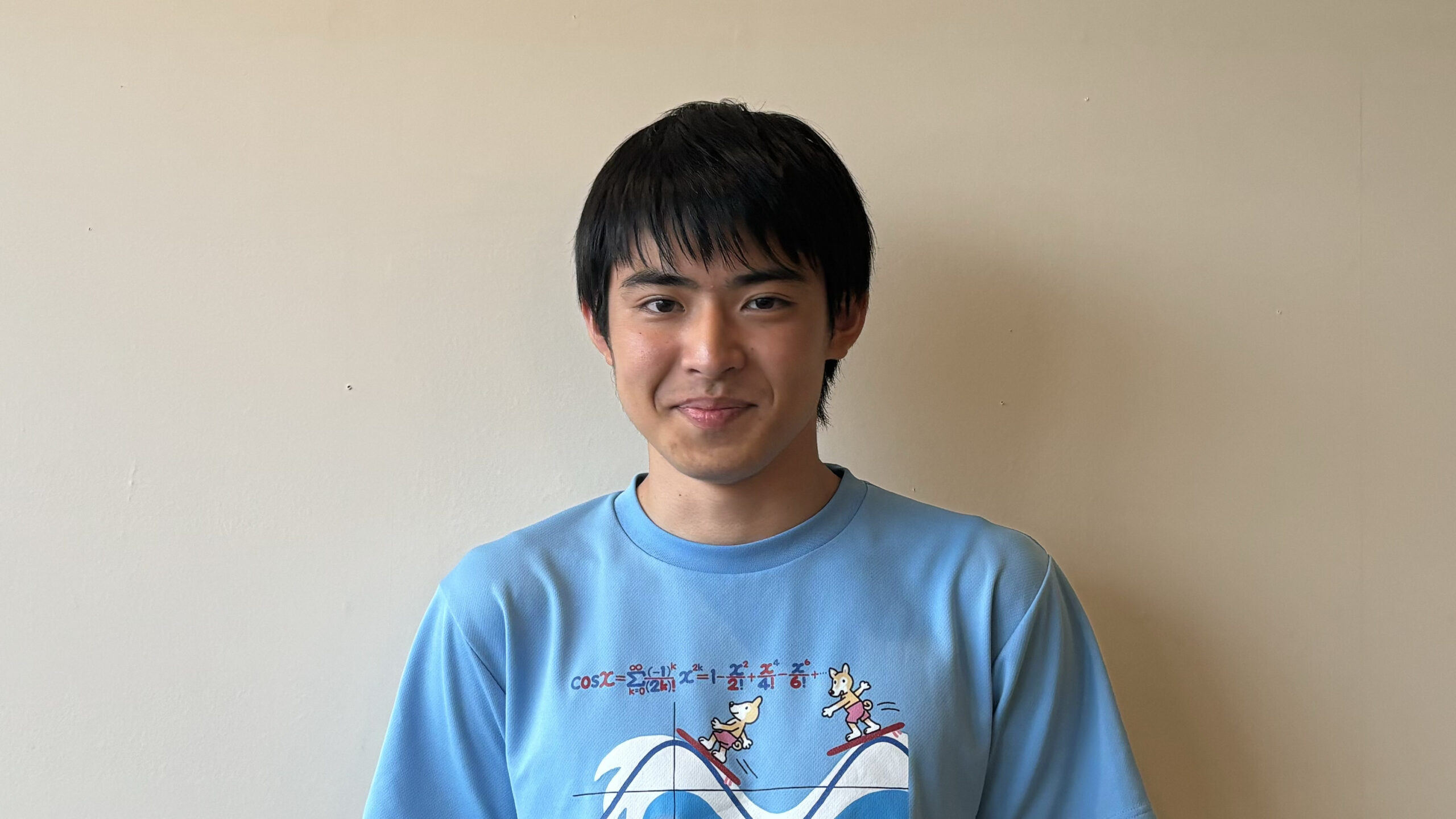高専起業家ショッキングの記念すべき最初のインタビューです!
本企画では、「高専生起業家の輪」を広げて、繋げていくことを考えています。
- 高専起業家をひとりひとり、点でインタビューするのではなく、紹介で繋いでいく。
☞インタビューの最後に、次の起業家を紹介してもらう!
- まずは「一つの輪」を広げていく、2つ、3つと広げて重なるのも面白い!
- インタビューを受けてくれた人の繋がりを相関図としてまとめてみる!
☞直接繋がってなくても、一緒に仕事をできる仲間が見つかるかも……?
起業家ショッキングの企画はこちらにまとめています👇

株式会社レインボーブライト 代表取締役 永江健太郎さん
2023年の高専の4年在学中に、中高生向けのオンライン学習塾をメインに「株式会社レインボーブライト」を設立。
2025年現在も大学3年へ編入し、「学生」×「起業家」の二刀流で会社経営に取り組む永江健太郎さんに、事業の詳細や学生起業の経緯、今後の展望についてお話を伺いました!
株式会社レインボーブライトの3つの事業領域
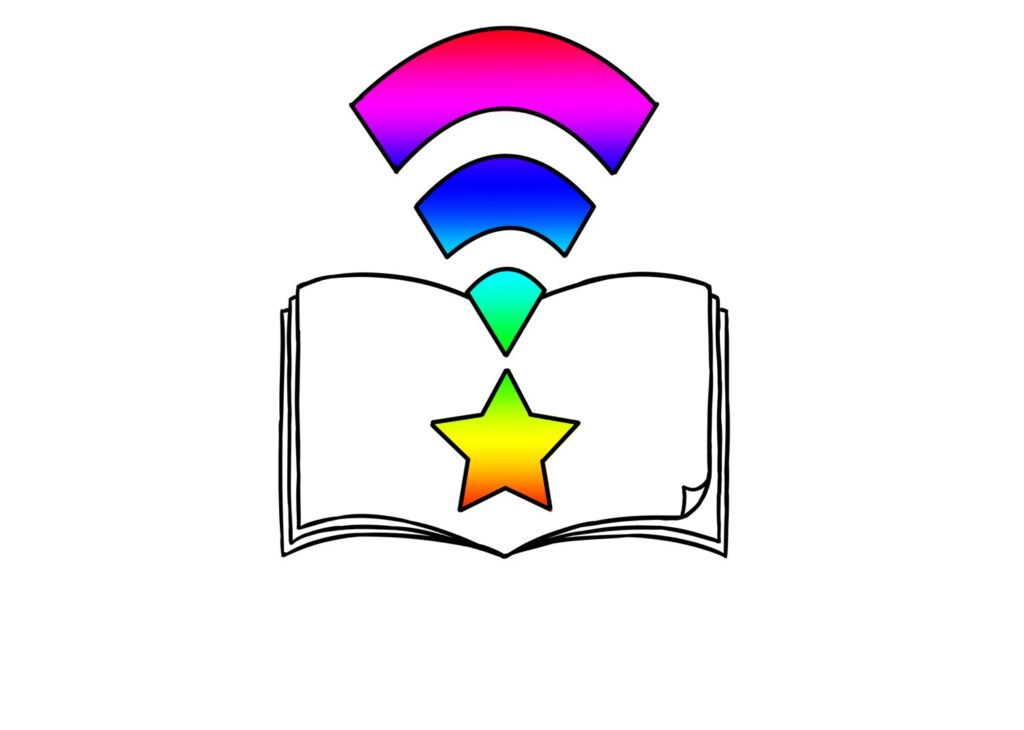
 マーティー
マーティー最初に、「株式会社レインボーブライト」の事業内容について教えてください。
「株式会社レインボーブライト」は、以下の事業を手掛けています。
- 教育業(学習塾運営、他塾提携)
- イベント運営(教育関連イベント、ワークショップなど)
- 受託事業(地域行事DX・WEB開発)
①教育事業としては、個別指導塾「レインボーブライト」を運営しています。
小学生から高校生まで、全学年を対象とした完全オンラインのマンツーマン指導塾です。
特に理系科目に強みがあり、数学や理科、情報分野などを中心にサポートしています。
レインボーブライトの大きな特徴は、指導を行っている講師が全員「高専生」または「高専卒業生」であることです。
高専は実践的な理工系教育で知られており、現役で技術や科学に触れている講師たちだからこそ、リアルな知識と学びを提供できるのが強みです。
生徒からも「理屈がちゃんとわかる」「応用力がつく」といった声を多くいただいています。
また、私たちは単に「問題が解けるようになる」ことをゴールにしていません。
レインボーブライトでは、「考え方を学ぶこと」「学び方を学ぶこと」を非常に大切にしています。
たとえば、よくある受験勉強では“この問題はこう解く”という暗記型のアプローチが多いですが、私たちはそうではなく、なぜその解き方になるのか、どうやってその答えにたどり着くかという“思考のプロセス”に重点を置いて指導しています。
その結果、生徒たちは目の前のテストだけでなく、その先の大学入試や実社会でも通用する“学ぶ力”を自然と身につけていきます。
現在は、この塾での知見や指導メソッドを活かして、EdTech分野への展開も視野に入れて準備を進めているところです。
より多くの子どもたちに、「考える力」を育む教育を届けられるよう、教育とテクノロジーを融合させた新しいサービスを開発していきたいと考えています。
EdTech(Education × Technology)事業は、教育にテクノロジーを活用する分野。
オンライン学習、AI教材、教育アプリ、学習管理システム(LMS)などが含まれます。
目的は「学びの効率化・個別化・アクセスの拡大」です。
《特徴》
- オンライン教育:時間・場所に縛られずに学習可能
- AI・データ活用:個人に合わせた学習進捗の最適化
経済産業省のHPより抜粋
②イベント運営の一例として、九州の高専生を対象としたハッカソンの企画・運営を行っています。これまでに2回開催し、いずれも30名以上の学生が参加しました。
参加費は無料とし、交通費の一部を補助しています。
また、参加者向けに宿泊場所も提供しており、学生ができるだけ少ない負担で参加できるイベントを目指しています。
九州高専ハッカソンの公式ページはこちら
ハッカソンとは、短期間でアイデアを形にする開発イベントのことです。
「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた言葉で、エンジニアやデザイナーなどがチームを組み、数時間〜数日間でアプリやサービスなどを開発します。
目的は、創造力と技術力を活かして課題を解決することです。企業や学校、地域イベントなどで開催されることも多く、初心者向けのものもあります。
③受託事業(地域行事DX・WEB開発)としては、佐世保を拠点に地域企業向けのWEBサイト制作を行っています。
また、地元イベント「YOSAKOIさせぼ祭」では、従来アナログだった採点システムをデジタル化し、運営の効率化を図りました。
こうした取り組みを通じて、地域活性化にも貢献しています。
「教える楽しさ」がすべての始まりだった——教育事業を志した原点



「教育事業」を中心に起業しようと思われた経緯や想い、きっかけなどについて教えてください。
中学3年生の1月、推薦入試で高専への内定が決まったことで、一足早く受験を終えることができました。
そこから卒業までの期間、放課後の時間を使って、まだ受験を控えている同級生に対して、授業のようなかたちで高校受験の勉強を教えるようになりました。
自分なりに工夫しながら「どうやったら理解してもらえるか」を考え、伝える喜びを感じたのが、教育に興味を持つ最初のきっかけです。
この経験が、初めて「人に教える」という行為の楽しさとやりがいを感じた瞬間であり、自分の中での教育の原点となりました。
高専入学後もその興味は続きました。
低学年の時は塾講師の採用もなかったため、ボランティアでコミュニティセンターでの勉強会を開くなどの活動を行っていました。参加費は場所代として¥100だけ頂いてましたが、後に無料でやることがよくなかったと気づきました。
当時は、できるだけ安いor無料がいいと思っていましたが、無料だと教える側の責任が弱まります。また、生徒側も有料の方が「せっかく払ってるから頑張ろう」と意欲がでやすいです。
高専3年の時には、とある塾でアルバイト講師として教える機会を得ました。
当時は「令和の虎」という起業家向けのYouTube番組にも影響を受け、教育に情熱を注ぎながら、自分自身がビジネスを立ち上げる姿を具体的にイメージするようになりました。
教えることの面白さ、誰かの成長に関われることの喜び、そしてそれを自分の手で事業として広げていける可能性。それらが重なり、私は教育事業での起業を本気で目指すようになりました。
中学生の頃、私の周囲にはテストで常に高得点を取る、いわゆる「優等生」と呼ばれる友人がいました。
その中の一人が、高校進学後に学習面で苦戦しているという話を聞いたとき、大きな衝撃を受けました。
「なぜあんなに優秀だった彼が、高校でつまずくのだろう?」と。
その問いをきっかけに、私は「テストの点数が良いこと=本当に学力があること」とは限らないのではないか、と考えるようになりました。
点数を取るための“やり方”を身につけることももちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、「なぜそうなるのかを考える力」や「自分で学び続ける力」、つまり“考え方”や“学び方”そのものを育むことだと感じました。
そして、「そんな力を育てる場を、自分の手で作れないだろうか」と思い立ちました。
単なる勉強の場ではなく、生徒一人ひとりが自分の頭で考え、自分のペースで学び、自分なりの方法で成長していけるような、そんな場所です。
その想いを形にするために、2022年8月、私は個別指導塾「レインボーブライト」を立ち上げました。
レインボーブライトという名前には、「一人ひとりが自分らしく輝けるように」「多様な色(価値観)を尊重する」という想いを込めています。
学びを通じて、ただ点数を伸ばすのではなく、自分自身を知り、未来に向かって歩む力を身につけてもらえるような塾を目指しています。



中学時代から現在にかけての永江さんの経験が「教育事業」に繋がったのですね!
企業理念にもその想いが現れています。
- 一人ひとりに寄り添う
生徒一人ひとりの個性と可能性を大切にし、それぞれに最適な学習環境を提供します。レインボーブライトHPより引用
- 地域に根ざした教育
地域の特性を活かし、地元に貢献できる人材の育成を目指します。- 未来を創る教育
変化する社会に対応できる思考力と創造力を育む教育を提供します。
動けるのは夜と週末だけ。学生起業家が抱えた最大のジレンマ



学生をしながらの起業は大変だったと思います。
その中でも「最大の壁や課題」と言えるものがあれば教えてください。
やはり平日の昼間にフルで稼働できないことは、今もずっと課題に感じています。
学生なので、当然ながら授業がありますし、レポートや実験などの課題も多いんです。
やりたいことや進めたいプロジェクトがあっても、どうしても動ける時間が限られてしまって、「自分が本気を出せるのは夜と週末だけ」というもどかしさをずっと感じています。
特に、教育事業だと保護者の方と日中に連絡を取り合ったり、行政や企業と打ち合わせをしたりする必要も出てくるので、「時間的に自分が動けないこと」がボトルネックになることが多いですね。



学生ならではの悩みですね。
他にも、苦労されていることはありますか?
もうひとつ大きいのは、社会人としての経験がまったくない中で、事業をどう回していくか手探りで進めている点です。
例えば、契約書の作成や交渉の進め方、財務の管理など、ビジネスの基本を学びながら実践する必要があるので、正解がわからないまま走っているような感覚があります。
もちろん、わからないことは調べたり、人に聞いたりして乗り越えてきましたが、どうしても「これでいいのかな…?」という不安を抱えながら判断している部分もあります。
とはいえ、そうした経験すべてが自分にとっての学びになっているので、苦労と同時に成長も感じています。



逆に、そのような制約の中で起業するからこそ、得られるものも多そうですね!
限られた時間、限られた知識の中で試行錯誤してきたからこそ、物事を柔軟に考える力や、失敗を前向きに捉える姿勢が身についたと思っています。
完璧じゃなくても一歩踏み出すことの大切さを、起業を通じて強く実感しています。
起業して気づいた「高専の学び」が活きる瞬間





起業して、会社を経営していく中で、高専での学びが活きた事例があれば教えてください。
高専での学びが活きていると実感する場面は多々あります。
特に印象的なのは、「学習の転移」という感覚を、在学中に自然と身につけていたことです。
高専では、たとえば数学で学んだ微分積分やベクトルの知識が、そのまま電気や機械、情報などの専門科目で応用されるんですね。
つまり、「これは何のために勉強するんだろう?」ではなく、「これがここで使えるんだ!」という体験を日常的にしていました。
知識を知識のままで終わらせず、実際の課題解決にどう活用するかを常に考える。
その姿勢が、今の教育事業にもすごく役立っています。
たとえば、塾でのカリキュラム設計や、生徒ごとの指導戦略を考えるときも、ただ教科書通りに進めるのではなく、「この子の状況だと、このやり方が合いそう」「この問題の構造は、実は別の分野の考え方が応用できるかも」といったように、分野横断的な発想を自然としています。
これってまさに、高専で培った「横につなぐ力」だと思っています。
また、論理的に物事を考える力や課題解決のプロセスを逆算で組み立てる力も、経営においては欠かせません。
何か問題が起きたときに、感情や直感だけに頼らず、「なぜ起きたのか」「どうすれば防げるか」を冷静に分析する力は、高専時代のレポートや実験、プレゼンの積み重ねで自然と身についたものです。
経営というと一見、文系の領域に見えるかもしれませんが、実際には理系的な思考力が求められる場面がたくさんあります。
「問題に対してどうアプローチするか」を構造的に考えるという意味で、高専での学びはまさに土台になっていますね。
「自分の挑戦」から「誰かの期待に応える仕事」へ――3期目の心境の変化



会社設立から3期目となりました。
ご自身の進学など、環境の変化もあったと思いますが、起業当時から心境面での変化はありますか?
起業当初と比べると、心境の面では大きく変わった部分があります。
設立当初は、「とにかく目の前のことを形にすること」に必死でした。
まずは自分の思い描いていた個別指導塾を立ち上げて、生徒を集めて、授業を提供する
――という、わかりやすい目標に向かって全力で動いていた感覚です。
ですが、会社として3期目に入り、少しずつ学習塾以外のお仕事やご相談をいただくようになってきました。
たとえば、他の教育系事業者との連携や、地域のイベントへの協力、WEBサイト制作の話など、当初は想定していなかったような仕事も増えてきています。
そうした中で、「これはもう自分一人の挑戦ではないな」と感じる瞬間が増えてきました。
自分が引き受けた仕事には、誰かの期待があり、責任があり、成果が求められる。
だからこそ、やりがいと同時に責任の重さも感じるようになりました。
以前は「まずやってみよう!」という勢いが先に立っていたのですが、今は「どう実現するか」「どう継続させるか」を深く考えるようになりましたね。
とはいえ、まだまだ未熟ですし、毎日が学びの連続です。
でも、事業を通じて「自分自身が育っている」実感があるのは、大きなモチベーションになっています。
教育事業と教員の道、どちらも大切にしたいこれからの人生設計



大学を卒業して、これから社会人になっていきますが、本事業の進め方や人生設計のようなものがあれば教えてください。
まず事業については、今やっている学習塾は、自分自身の想いや経験が強く反映されている、いわば「属人性の高い」事業だと思っています。
だからこそ、完全に仕組み化して人に任せてしまうというよりは、自分の目が届く範囲でしっかりと関わり続けたいという気持ちが強いです。
もちろん、必要に応じてシステム的に効率化する部分もあるとは思いますが、それでも「生徒一人ひとりに寄り添う」という本質的な価値の部分は、自分が関わりながら守っていきたいと思っています。
なので、急拡大ではなく、あくまで丁寧に、目の届く範囲での事業拡大を目指していきたいですね。
それと並行して、将来的には学校現場で教員として働きたいという思いも持っています。
これは中学生の頃に友人に勉強を教えた原体験や、高専・大学を通じて教育に向き合ってきた経験から生まれた夢でもあります。
現場で生徒と向き合いながら、自分の教育観を活かしていけたら嬉しいです。
起業という選択をしたことで、「教育にはいろんな形がある」と気づくことができましたし、それは今後、教員という立場に立ったときにも大きく活きてくると思います。
教室の中だけではなく、外にも学びの場が広がっていることを、自分自身が体現していきたい。
そういう意味では、事業と教員、両方の道を大事にしていきたいと考えています。
人生設計といえるほど明確な道筋があるわけではありませんが、自分が情熱を持てる領域で、人の成長に関われる仕事を続けること。それが今の時点での、いちばん大切にしている軸ですね。



将来は教員になりたいんですね!
起業と教員の両立をするために、今後考えていることはありますか?
まさに今、そこは自分自身の大きなテーマだと思っています。
両立というと、時間的にもエネルギー的にも難しい印象があるかもしれませんが、私の中では「二足のわらじ」というより、「異なる視点から教育に関わること」だと捉えています。
具体的には、将来的に教員として学校現場で働くことを見据えながら、今の事業を無理のない規模に整えていくことが大切だと考えています。
また、いずれは塾の運営を支えてくれる仲間や後輩、高専生たちに指導や運営の一部を任せられるように体制を整えていきたいと考えています。
自分一人がすべてを抱えるのではなく、共通の教育理念を持ったチームで生徒を支えていけるような仕組みにしたいですね。
一方で、学校現場では、やはり“制度の中”での教育になります。
そこでこそ気づけることや、制度の限界も含めたリアルな課題に直面するはずなので、学校の中で得た気づきを事業にフィードバックし、逆に塾や事業での経験を学校に活かす——そんな循環をつくるのが、私の理想です。
教育には一つの正解がなくて、多様な手段や場面があります。
その中で、「教員としての自分」と「起業家としての自分」が、互いを補い合いながら成長していけるようなキャリアを築いていきたいと考えています。
不安があっても大丈夫。大切なのは、小さくても動いてみること



最後に、起業したいけど一歩目が踏み出せない人へアドバイスをお願いします。
私自身もそうでしたが、最初の一歩って本当に勇気がいりますよね。
「うまくいかなかったらどうしよう」とか、「自分にはまだ早いんじゃないか」とか、不安や迷いは誰にでもあるものだと思います。
そんなときにおすすめしたいのは、いきなり大きなことを始めようとせず、まずは“自分のできること”から始めてみることです。
たとえば、自分の得意なことや好きなことを活かして、アルバイト以外のかたちで1円でもお金を稼ぐ経験をしてみる。それがすごく大事だと思っています。
私の場合は、学生時代に勉強を教えることが好きだったので、塾のアルバイトをきっかけに、やがて個人で指導を始め、そこから少しずつ事業として育てていきました。
最初は月に数千円だった収入が、やがて少しずつ形になっていった。
それは「小さな成功体験」を重ねたからこそ、続けることができたんだと思います。
起業というと、会社を立ち上げたり、大きな資金を調達したり、ビジネスプランを練り上げたりと、ハードルが高く見えるかもしれません。
でも、本当に大事なのは“最初の一歩”を踏み出すこと。
そしてそれは、思っているよりもずっと小さくていいんです。
たとえば、SNSで自分の考えを発信するだけでも、誰かと一緒にアイデアを話し合うだけでも、それは立派な一歩です。
その小さな一歩を繰り返していけば、気づいたときには、自分だけの事業が形になっていると思います。
なので、「自分にはまだ早い」と思わずに、まずは“試してみる”気持ちで、スモールスタートを切ってみてほしいです。
やってみたからこそ見える世界が、必ずあると思います。
インタビューを通じてのまとめ
高専での学びを活かしながら、学生時代に起業し、個別指導塾「レインボーブライト」を立ち上げた永江さん。
その根底には、「考える力を育てる教育を届けたい」という一貫した想いがありました。
学生起業ならではの、時間的制約や経験不足といった壁にも直面しながら、一歩ずつ試行錯誤を重ねてきた3年間。
今では、教育だけでなく地域やIT領域にも活動を広げ、多面的に社会と関わっています。
これからは教員という道も視野に入れつつ、「教室の中」と「事業の現場」両方から教育に関わる未来を目指しているとのこと。
「まずはできることから始めてみる」——その姿勢が、迷いを抱える人たちにとって大きなヒントになるはずです。



貴重なお話を頂き、ありがとうございました!
「高専起業家ショッキング」企画で紹介してくれたのは、小池勇琉さん。
小池勇琉さんとは、同じ佐世保高専出身の先輩・後輩という関係です。永江さんが4学年下ですが、5年生の高専では同じキャンパスにいたことになります。
ただ、永江さんは電気電子工学科、小池さんは電子制御工学科と、学科が異なるため在学中は直接の接点はなかったそうです。
そんな二人がつながったのは、起業家イベント「Startup Weekend」や「長崎学生ビジネスプランコンテスト」での再会がきっかけでした。
ここから、同じ高専出身という共通点を持つ起業家同士の交流が始まります。
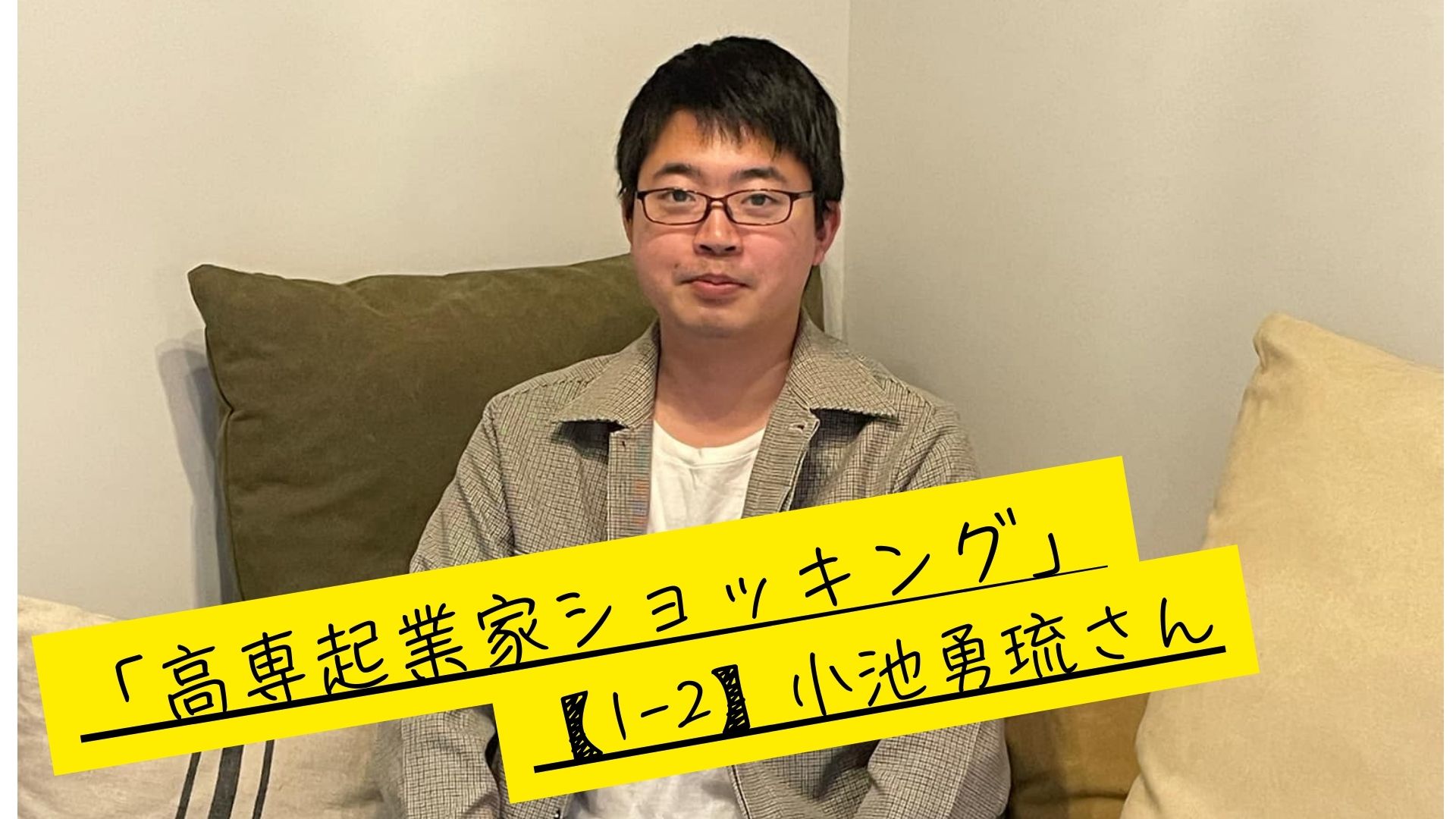
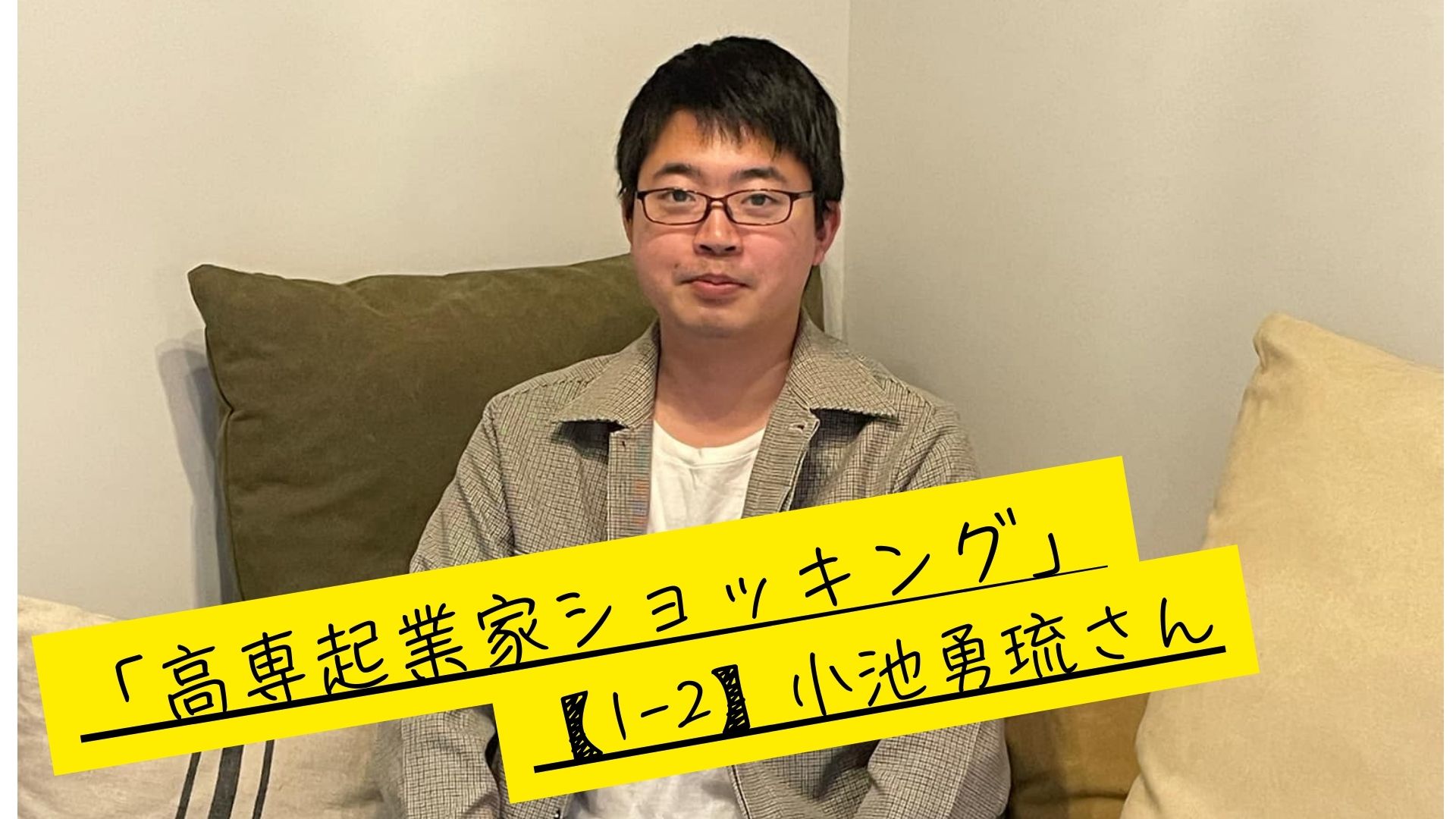
プロフィール:永江健太郎さん
2020/04~2025/03 佐世保高専
2025/04~ 長岡技術科学大学(在学中)
2023/04~株式会社レインボーブライト代表取締役
企業情報
| 法人名 | 株式会社レインボーブライト |
| HP | 学習塾レインボーブライト |
| 設立 | 2022年8月(個人事業主として開業) 2023年4月(法人設立) |
| 事業内容 | 教育業(学習塾運営、他塾提携) イベント運営(教育関連イベント、ワークショップなど) 受託事業(地域行事DX・WEB開発) |
永江健太郎さんの過去のインタビュー記事はこちら👇